AWSにおいて求められるCCoEとは?主な機能や役割、構築方法やポイント
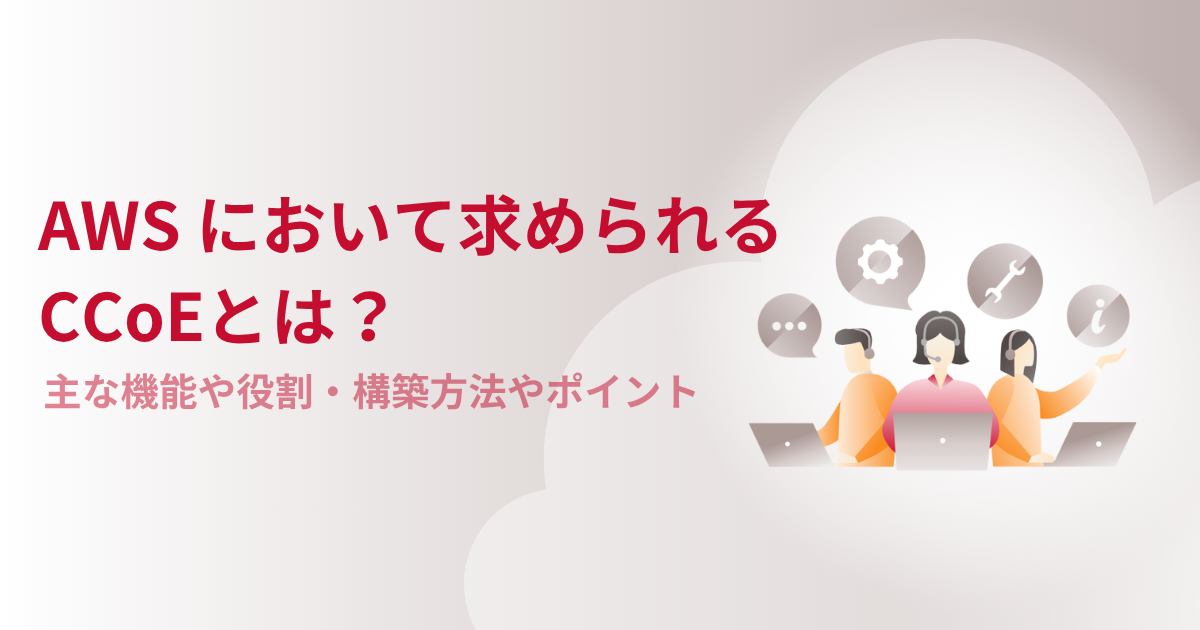
近年、クラウドサービス活用の加速やマルチクラウド環境の拡大に伴い、各部門に運用が分散することによるガバナンス不全やコスト増大、セキュリティリスクの顕在化といった課題が浮上しています。本記事では、全社横断でクラウドサービス戦略を推進する「CCoE(Cloud Center of Excellence)」について解説します。
この記事でわかること
- CCoEの概要と業務効率改善などのメリットに関する具体例
- CCoE構築のステップにおけるポイント、実務で役立つノウハウ
- CCoe導入ケース、技術支援サービス活用のヒント
※当記事は2025年6月に書かれたものであり、以後に展開された最新情報が含まれていない可能性がございます。
CCoEに関する基礎知識
まずはCCoEの基本から確認しましょう。CCoEとは何を指し、なぜ企業で注目されているのか、その背景を解説します。
そもそもCCoEとは
CCoE(Cloud Center of Excellence)とは、「クラウド活用推進のために必要な人材や知識、リソースを一箇所に集約した全社横断型の組織」を指します。言い換えると、企業内でクラウド戦略を遂行し、技術を最大限に活用するための社内専門チームです。部署の垣根を越えてクラウドサービスに精通したメンバーを集め、統一方針のもとでクラウド導入・運用の支援やガイドライン策定などを行います。 クラウドサービスはビジネスにおいて欠かせないITインフラとなりつつありますが、その導入・活用を各部署任せにしていては十分な効果を得られません。そこでCCoEという専任組織を立ち上げ、クラウドサービス活用を全社的に統率してその恩恵を最大化しようという取り組みが広がっています。なお、アマゾン ウェブ サービス(AWS)公式もクラウド導入成功の鍵としてCCoEの重要性を強調しており、2016年のブログでも社内に専門チームを設けることを推奨しています。
なぜCCoEが求められるのか
CCoEが近年多くの企業で注目されるのは、大きく分けて2つの理由があります。
1つ目は、クラウド化をスムーズに推進するためです。個々のチームや部門ごとにクラウド導入を進めても、最適化の範囲が限られてしまい全社としての効果が頭打ちになるケースが少なくありません。一方、CCoEという横断組織があれば、各部門間の調整やロードマップ策定、共通のクラウド利用ガイドライン整備などを一括して行えるため、クラウド導入の加速と社内調整の円滑化が期待できます。実際、DXを推進したい企業ではトップダウンでクラウド活用を打ち出す際に、旗振り役としてCCoEを設置する例も増えています。
2つ目の理由は、セキュリティリスクを低減するためです。クラウドサービスの普及に伴い、現場が独自判断でクラウドを利用するシャドーITが生まれやすくなりました。結果として、社内のあちこちにIT部門の管理が及ばないクラウドが乱立し、ガバナンスが効かなくなる懸念があります。CCoEはこうした無秩序なクラウド利用を防ぎ、統一されたセキュリティポリシーとITガバナンスの下でクラウド活用を管理します。言い換えれば、CCoEはクラウド推進の"アクセル"であると同時に、リスクに備える"ブレーキ"でもあります。
CCoEの主な機能と役割
次に、CCoEが具体的にどのような役割を果たすのかを見ていきましょう。クラウド戦略の策定から社内への展開まで、CCoEには多岐にわたる機能があります。
クラウド戦略の策定
CCoEの重要な役割の一つが、クラウド戦略の策定です。自社のビジネス課題を解決し競争力を高めるために、クラウドをどのように活用するか長期的な方針やロードマップを描きます。例えば「どのシステムをいつまでにクラウド化し、どんな効果を得るか」といった目標を定め、できるだけ定量的な指標で測定できるようにします。戦略を明確にすることで、クラウド化それ自体が目的化しないようにすることです。あくまでビジネス目標達成の手段としてクラウド活用を位置付けましょう。
ベストプラクティスの共有
ベストプラクティスの社内共有も、CCoEの大切な役割です。CCoEはクラウド活用の最新動向や成功事例、技術的な知見を収集して組織内に蓄積します。そしてそれらを社内向けに発信し、各部門が最適な形でクラウドを利用できるよう指南します。具体的には、クラウド設計・運用に関するガイドラインや標準的なアーキテクチャを整備して展開したり、勉強会やコミュニティを通じてナレッジ共有を図ったりする活動が含まれます。CCoEが中心となって情報共有を推進することで、どの部門でも一定の水準で効率的かつ安全にクラウドを活用できるようになります。
コストの最適化
クラウド利用コストの最適化もCCoEの重要な役割です。全社的に利用状況を可視化し、不要リソースの停止や適切なリソース選定によるコスト削減を推進します。さらに、部門横断で予算を統合管理し、費用対効果を最大化します。
ガバナンスの確立
クラウドガバナンスの確立も、CCoEの中心的な役割です。クラウド導入に伴うセキュリティやコンプライアンスの課題に対し、全社統一のルールと管理体制を構築します。現場が安心してクラウドを活用できる環境を整え、全社でセキュリティ水準を維持します。まさにCCoEはクラウド活用の「守り」の部分を担う存在と言えるでしょう。
ナレッジの収集と人材育成
CCoEのもう一つの重要な役割が、社内のクラウドナレッジの集約と人材育成です。クラウドに関する最新情報やノウハウを社内に共有し、各部署の知識格差を埋めていきます。また、クラウド人材の育成においても、研修制度の整備や勉強会の開催、資格取得支援などを通じて社員のスキル向上を図ります。CCoEが中心となってナレッジとスキルの底上げを行うことで、企業全体でクラウドを活用できる人材基盤が育っていきます。
CCoEの構築方法
ここでは、実際に自社でCCoEを立ち上げる方法についてステップごとに説明します。目的設定からメンバー選定、社内展開、そして継続的な改善まで、順を追って見ていきましょう。
自社の目的を明確にする
CCoE構築の第一歩は、CCoEを導入する目的やビジョンを明確にすることです。まず「クラウドを活用して自社は何を達成したいのか」「CCoEにどんな役割を期待するのか」を経営層で擦り合わせ、目標を定めます。この目標は可能な限り定量的な指標で表し、後から効果測定できる形にすると良いでしょう。例えば、「オンプレミス環境の既存システムをクラウドサービスに移行して1年で運用コストを20%削減する」や「クラウド活用で新規サービスの立ち上げ速度を倍にする」など、具体的な数値目標を設定します。 重要なのは、クラウド化自体が目的化しないようにすることです。クラウドはあくまでビジネス目標達成の手段であり、目的そのものではありません。経営層から現場まで目指す方向を共有し、全社で同じゴールを見据えることが大切です。
メンバーを確保する
目的・計画が固まったら、CCoEを構成するメンバーを確保しましょう。CCoEのメンバーは、クラウド技術の専門家はもちろん、経営層、IT企画・開発担当、財務担当、クラウドを利用する現場部門の代表者など、社内の幅広い利害関係者で構成します。自社に十分なクラウド人材がいない場合は、エンジニアを育成したり社外から採用したりすることも検討しましょう。また、外部のクラウド専門企業に相談して支援を受けるのも一つの方法です。重要なのは、「クラウド推進に情熱を持つ人」を集めることです。スキルや肩書き以上に、クラウドで会社を良くしたいというマインドを持ったメンバーこそがCCoE成功の原動力になります。
| 役割 | 役割・期待される貢献内容 |
|---|---|
| クラウド技術の専門家 (クラウドエンジニア) |
クラウド環境の設計・構築をリードし、ベストプラクティスを社内に共有する。 |
| 経営層 | CCoE設立の意思決定と全社的コミットメントを行う。 |
| IT企画・開発担当 | ビジネス要件を技術要件に落とし込み、クラウドロードマップを管理する。 |
| 財務担当 | クラウドコストの予算管理と費用対効果分析を実施する。 |
| 現場部門の代表者 | 各部門のニーズをCCoEへ伝え、導入後の運用調整を担当する。 |
| 外部クラウド専門企業 | 技術アドバイスやワークショップ提供などで支援を行う。 |
全社にアナウンスをする
メンバーが決まりCCoEが発足したら、全社へのアナウンスを行います。ここでは可能な限り経営トップから社内発信してもらうことがポイントです。トップ自ら宣言することで、CCoEの存在が社内に広く周知され、経営の後ろ盾がある組織だと示せるため各部門から協力を得やすくなります。単にCCoEを作るだけでなく、全社的な連携・協力を得て初めて効果が発揮される点を認識しておきましょう。
導入のサポートを行う
CCoE立ち上げ後は、各部門でのクラウド導入を実行支援していきます。具体的なサポート内容として、クラウド導入時のセキュリティやコストに関するガイドライン策定、クラウド活用事例やノウハウの社内共有、複数部門にまたがる課題への調整支援、そして社内でのコミュニティ整備などが挙げられます。これらを通じて全社のクラウド化がスムーズに進むよう環境を整えるのがCCoEの役目です。
PDCA サイクルを回す
クラウド導入が進んだ後も、継続的な改善(PDCAサイクル)を回し続けることがCCoEには求められます。例えば、クラウドの利用ログやユーザー要望といったフィードバックを分析し、設定変更やツール導入などの改善策に反映します。このように定期的な検証と改善を重ねることで、CCoEは組織に根付いた改善のエンジンとして機能し、クラウド活用の成果を最大化していきます。
CCoEを導入する際のポイント
CCoEを成功させるために押さえておきたいポイントを紹介します。いきなり完璧を目指すのではなく段階的に進めること、組織横断のメンバー構成、そしてツールの活用による効率化が鍵となります。
段階的に導入する
CCoEは最初から完璧な体制を整えて始める必要はありません。むしろまずは小さく始めることが大切です。すべての専門家を揃えてから始めようとすると、いつまでも着手できない恐れがあります。最初は一部の知見しかなくても構いませんのでCCoEを立ち上げ、クラウド運用を進めながら不足する知識は補い、ノウハウを蓄積していけばよいのです。実際にクラウドを導入・運用する中で見えてくる課題も多いため、初めから完成形にこだわらず、まずはスモールスタートで走り出し、経験を重ねていきましょう。
利害関係者や経営陣をメンバーに加える
前述の通り、CCoEのメンバーには様々な部門から人材を集める必要があります。その際、利害関係者を広く網羅し、経営層にも参加してもらうことが成功のポイントです。クラウド推進の組織というとクラウド専門家やITエンジニアばかりに目が行きがちですが、それだけでは十分ではありません。クラウド導入は単なる技術導入ではなく業務改革を伴うため、現場・管理部門・経営陣を含めた幅広いメンバーで構成することが不可欠です。特に経営層の参画は必須と言えます。トップのコミットメントにより、クラウド推進が企業戦略として社内に浸透します。
ツールを導入する
CCoEに期待される役割の一つにセキュリティ管理があります。そこで躓かないためにも、すべてをマニュアルやガイドラインに頼らず、積極的にツールを導入する必要があります。もちろん基本は社員一人ひとりがセキュリティ意識を持って運用することですが、人手だけではミスや漏れをゼロにするのは難しいでしょう。例えば、セキュリティ対策としてパスワード管理や暗号化などの専用ツールを導入し、自動監査やモニタリングを強化することが有効です。また、設定の自動化など管理効率化の仕組みも積極的に導入しましょう。ツール活用によってヒューマンエラーの影響を最小限に抑え、クラウド利用を適切に統制できます。
CCoEの導入事例
最後に、実際にCCoEを導入して成果を上げている企業の例を見てみましょう。大規模企業の事例から、CCoEがどのように社内改革を進め、ビジネス価値を生み出しているかがわかります。
大手情報通信業
ある大手情報通信企業では、社内のクラウド有識者を集めてCCoEを立ち上げました。同組織は、社内業務のクラウド活用による効率化と、社内で得た知見を活用した顧客課題の解決提案という二つの役割を担っています。例えば、CCoE主導で自社のコールセンターシステムにAmazon Connect(クラウド型コンタクトセンターサービス)を導入したところ、通話履歴などコールセンターの指標を取得・分析できるようになり、業務改善や品質向上に役立てられるようになりました。さらにクラウド基盤を利用することで、問い合わせ急増時にも迅速に規模を拡大でき、顧客ニーズに応じた柔軟な対応が可能となっています。
大手印刷メーカー
国内大手の印刷会社でも2018年にCCoEが立ち上げられています。そのCCoEは、クラウド導入・運用に関する情報やノウハウを社内で収集・共有する拠点として機能しました。具体的な取り組みとして、クラウド設計ガイドラインの策定や共通セキュリティツールの整備、定例の情報共有会開催とクラウド研修の実施などが行われました。これらの取り組みにより、同社ではマルチクラウドの効果的な運用が可能となり、ビジネスへの貢献度も高まりました。
CCoEはクラウド活用の要
この記事で解説してきたように、CCoEはクラウド活用による企業変革の要となる組織です。CCoEをうまく機能させることで、単なるクラウド移行に留まらずビジネスの生産性向上や競争力強化、さらにはセキュリティ体制の強化まで実現できます。一方で、CCoEの立ち上げ・運営には社内横断の調整や高度な専門知識が求められるため、自社だけですべてを賄うのは難しい場合もあります。 そのようなときは、クラウド導入の経験が豊富なパートナー企業の力を借りるのも有効です。
サーバーワークスのクラウドシェルパは専任の技術チームが企業とともに課題解決に取り組む伴走支援サービスで、ガバナンス強化から最新技術の活用、人材育成まで包括的にサポートします。社内に十分なクラウド知見がない場合でも、こうした外部の力を借りれば安心してCCoEの立ち上げとクラウド活用を進められるでしょう。CCoEの導入によって、クラウドという強力な武器を企業全体で使いこなせるようになります。本記事を参考に、ぜひ自社のクラウド活用を次の段階へ引き上げるべく、CCoEの設立・運用に挑戦してみてください。




