AWSの生成AIを採用して安価で安全に全社で利用できる環境を構築、サーバーワークスの支援によりアクセス権の設定と追加機能の実装も実現

医薬医療向け、日用品や化粧品などの包装材や容器、情報電子、産業インフラなどの4つのセグメントで安定かつ幅広く事業を展開し創業110年を超えるZACROS株式会社では、2024年6月から研究所でRAGを含むSaaS型生成AIサービスの利用を開始。一方、情報システム部でも、生成AIの全社展開を見据えた生成AIアプリケーションの検証を始めていました。しかし、RAGの全社展開を実現するためにはアクセス権の制御が必須で、自社構築では多大な学習コストと手間がかかるという課題がありました。この課題を解決するために採用したのが、サーバーワークスの「RAG運用支援」です。当時の課題とRAG運用支援の効果、サーバーワークスに対する評価、今後の展望について、情報システム部 ITプラットフォームデザイングループの鈴木裕之氏、同 瀬戸あゆみ氏、情報システム部 IT-ビジネス推進グループの乗次太陽氏、同 渡辺義彰氏、研究所 研究推進センター 戦略グループの鈴木真一郎氏に、お話を伺いました。
事例のポイント
Before
お客様の課題
- 先行して利用していたSaaS型生成AIサービスを全社展開するためには費用が高額になると予想されたため、コスト的に断念せざるを得ない状況だった
- RAGの全社展開に必要なアクセス権の設定は、技術的に自社単独での実装が難しかった
After
課題解決の成果
- AWSの生成AIアプリケーションを採用し、全社展開を実現
- サーバーワークスの支援により、全社展開時のアクセス権の設定や利用効果測定機能を実装
導入サービス
Index
研究所でRAGの利用を開始、情報システム部でも全社展開を前提に生成AIアプリケーションの検証をスタート
2024年6月、ZACROSの研究所では、SaaS型生成AIサービスを利用したRAGの使用を開始しました。背景には、長年蓄積されてきた技術情報の有効活用という課題がありました。
当時の状況について、研究所の鈴木真一郎氏は次のように説明します。

鈴木真一郎氏「研究所には40年以上の技術情報を蓄積したデータベースがありますが、形式がバラバラで、必要な情報を得るには1件ずつ開いて確認するしかなく、検索性に大きな課題がありました」
この課題を解決するために、研究所ではRAG(検索拡張生成)の導入を決定しました。
※RAG:LLM(大規模言語モデル)の学習データに加え、外部のデータベースやドキュメントからも関連情報を検索し、参照して回答を生成する技術
鈴木(真)氏「当時、情報システム部でも生成AIの全社利用を検討していましたが、研究所ではSaaS型生成AIサービスを選択し、先行してRAGの使用を開始しました」
一方、情報システム部でも生成AIの全社展開を前提に、2024年4月から生成AIアプリ「Generative AI Use Cases (以下、GenU)」の利用を開始しました。GenUは、AWSの生成AIサービス「Amazon Bedrock」などを利用して、チャットボットや RAGといった多様なユースケースを1つのアプリケーションとして提供するものです。
GenUの選定理由について、同グループの鈴木裕之氏は、次のように説明します。

鈴木裕之氏「当社は以前からAWS環境を活用しており、データ分析基盤もAWSで構築していました。そうした既存環境との親和性を考慮し、GenUを選択しました」
RAGを全社展開する際の大きなハードルとなった導入コストとアクセス権の設定
同社がRAGの全社展開を検討する際、選択肢は2つありました。
1つは研究所で使用していたSaaS型生成AIサービス、もう1つは情報システム部が検証していたGenUです。
渡辺氏「GenUを使った研究所のメンバーからは、RAGにはまだ対応していなかったにもかかわらず、GenUのほうが回答精度が良いという声が上がっていました」
さらにコスト面では、SaaS型生成AIサービスとGenUには大きな差があることが分かりました。ユーザー部門の課題解決をITで支援するIT-ビジネス推進グループの渡辺義彰氏は、次のように振り返ります。

渡辺氏「SaaS型生成AIサービスは、1ユーザー単位の課金体系で、基本料金も含めてサービスを利用する全従業員分、積み上げると、高額になることが予想されましたが、GenUはそれよりも安価に抑えられることが分かりました」
この点について、鈴木裕之氏はさらに次のように続けます。
鈴木(裕)氏「もしGenUという選択肢が無かったら、生成AIサービスの全社展開を断念する、という判断になっていたと思います。その場合、当社の従業員は、業務で生成AIを利用する機会も、情報リテラシーを高めていく機会も失っていたはずです。GenUはこうしたリスクを完全に払拭してくれたと言えます」
一方でGenUを全社展開するに当たっては、アクセス権を設定するための技術実装が必要でした。
鈴木(裕)氏「Google WorkspaceとAWSでのユーザー認証を担うAmazon Cognitoとの連携は済んでいましたが、GenUでアクセス権を設定する段階で技術的な課題に直面し、私たちだけではその解決方法が分かりませんでした。自分たちだけで解決しようとすれば、多大な時間と学習コストがかかります。そこで信頼のおけるITパートナーに協力を依頼することにしました」
サーバーワークスのRAG運用支援で技術課題を解決、さらに効果測定できる機能も追加で実装
その際、同社が選択したのがサーバーワークスの「RAG運用支援」でした。RAG運用支援は、RAGの定量的な評価の導入などを通じて、お客様のRAG運用をサポート支援するサービスで、LLMを活用した評価やユーザーフィードバック分析を通じて課題を特定し、継続的な改善サイクルの確立を支援します。
鈴木(裕)氏「サーバーワークスとは以前からAWSの基盤構築などで取引があり、AWSからの紹介もありました。私たちの肌感覚での信頼感に加え、AWSからも評価されているITベンダーということで、他の選択肢はありませんでした」
こうしてGenUをベースとするRAGの全社展開は、2025年3月から5月の3か月間で実施され、同社ではコスト削減と技術課題の両方を同時に解決することができました。
そしてもう1つ、今回サーバーワークスの支援を受けて追加実装したのが、生成AI(=GenU)の利用効果を測定できる機能です。
渡辺氏「GenUとやり取りしたトークンとその内容のジャンルから判断して、何分くらいの業務時間削減ができたかを分析する機能です」
鈴木(裕)氏「定量的な効果としては、4か月間の集計で利用者1人当たり年間25日分の業務時間削減に相当します。全ユーザーでは、年間に換算するとおよそ35年分の削減効果です。定性的にも“別の業務に集中できるようになった”という声がヘビーユーザーから上がっています」
さらに、IT-ビジネス推進グループの乗次太陽氏は、従業員の生成AIに対する関心の高まりを実感していると強調します。

乗次氏「GenUを全社展開したことで、生成AIに対する問い合わせなど、従業員から直接の声を聞く機会が多くなりました。社内のITリテラシーが向上しつつあることを強く実感しています。また、GenUへのログインやトークン数などの利用状況を確認すると、社内の意外なユーザーや部署が興味を持っていたりヘビーユーザーだったりすることが把握できるので、情報システム部としては、今後のIT戦略を考える上での参考にもなっています」
この他、2025年7月のGenUの評価に対する利用者の回答では、Goodを占める割合が約98%で、2025年3月の94%と比較し、評価自体も非常に高いものとなっています。
また、GenU利用者数も着実に拡大しており、2025年7月は431名が利用しています。これは 2025年6月の408名から前月比105%、5月の363名から前々月比118%の増加に相当し、社員のGenUへの関心も高まっているといえます。情報システム部では今後もこれらのKPIを測っていく予定です。
プロジェクト管理を高く評価、今後も緊密なパートナーシップに期待
今回のプロジェクトを通して、同社ではサーバーワークスの対応を高く評価しています。初めにITプラットフォームデザイングループ 瀬戸あゆみ氏は、サーバーワークス内の有機的な連携を挙げます。

瀬戸氏「サーバーワークス側の役割分担が非常に明確でした。メインでヒアリングを担当するエンジニアの方、認証・アクセス権限の技術を担当するエンジニアの方といった形で、有機的に連携していただきました。レスポンスも非常に早く、即日で回答をいただけることも多かったので助かりました」
乗次氏「今回は使い勝手向上のために、GenUのデフォルトのUIの修正もお願いしたのですが、サーバーワークスにとっては任意の要件だったにも関わらず、しっかりと対応していただけたことは、本当に心強かったです」
渡辺氏「また、プロジェクト管理ツールのBacklogを利用したタスク管理や構造化された議事録がとても分かりやすく、参考になりました」
一方、今回のプロジェクトについて、サーバーワークス営業担当のカスタマーサクセス本部 営業2課の伊藤響、技術担当のカスタマーサクセス本部 CS4課 課長の村上博哉、同じく技術担当のカスタマーサクセス本部 CS5課 近藤諒都は、次のように振り返ります。
伊藤「生成AI の活用においてセキュリティ・ガバナンスの要件は切っても切り離すことができず、特にRAGの全社展開を目指されるお客様にとって、アクセス権限の設定はほぼ必須の要件と言っても過言ではないと思います。生成AIはアップデートも激しいため、全社展開後もRAGの精度向上や最新アップデートの共有など、伴走支援をベースに運用のお手伝いをさせていただければと思います」
村上「先に乗次様からお話のあったUIの修正などは、エンドユーザー様の利便性や業務効率を考えた時には非常に大きなポイントです。そうした部分にもきめ細かく対応できるのが、AWSとお客様の間にいるサーバーワークスの大きな強みだと考えています」
近藤「今回課題となったアクセス権の設定では、対象部署をどんな単位で分類すれば、より効率的かを考える必要があります。そのためにお客様へのヒアリングを行い、それを受けて色々なフォルダの分け方をご提案させていただきました。RAGの全社展開を考えている他の企業様にとっても重要なポイントです」
今後も同社では、生成AIの社内利用率についての情報提供や技術的なアドバイスなど、サーバーワークスとの緊密なパートナーシップに期待を寄せています。
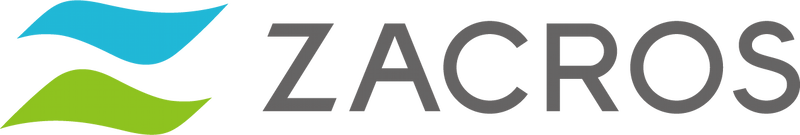
ZACROS株式会社様
医薬医療用包装材やバイオ医薬品製造時に使用するシングルユースバッグを扱う「ウェルネス事業」、日用品や化粧品などのつめかえパウチを扱う「環境ソリューション事業」、液晶保護フィルムや電極材を扱う「情報電子事業」、トンネル用の防水シートなどを扱う「産業インフラ事業」など4つのセグメントで幅広く事業を展開。創業110周年を迎えた2024年には、サービス/機能/仕組みのソリューションをグローバルに提供し続け、ソリューション創造活動を進化させるために、社名を藤森工業株式会社から現在のZACROS株式会社に変更した。
取材に協力いただいた方々
- 鈴木裕之氏
- ZACROS株式会社 情報システム部 ITプラットフォームデザイングループ
- 瀬戸あゆみ氏
- ZACROS株式会社 情報システム部 ITプラットフォームデザイングループ
- 乗次太陽氏
- ZACROS株式会社 情報システム部 IT-ビジネス推進グループ
- 渡辺義彰氏
- ZACROS株式会社 情報システム部 IT-ビジネス推進グループ
- 鈴木真一郎氏
- ZACROS株式会社 研究所 研究推進センター 戦略グループ
※ この事例に記述した数字・事実はすべて、事例取材当時に発表されていた事実に基づきます。数字の一部は概数、およその数で記述しています。
担当プロジェクトメンバー
-
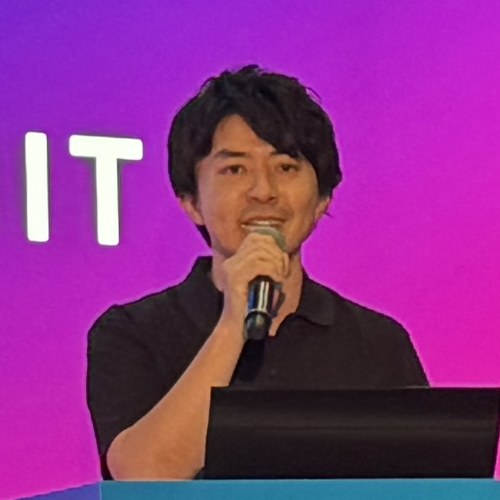
カスタマーサクセス本部 CS4課 村上 博哉
2024-2025 Japan AWS Top Engineers (AI/ML Data Engineer)。2020年にAmazon Pollyと出会ったことをきっかけに、前職の市役所職員からサーバーワークスへ転職。機械学習に興味があり、現在は生成AIを中心にお客様の支援を担当。好きなAWSサービスはAmazon SageMaker
-

カスタマーサクセス本部 CS4課 櫻庭 優志
様々な分野の業務アプリケーション開発に10年弱携わった後、2024年にサーバーワークス入社。アプリ開発の知見も活かしつつ、生成AI関連の支援業務に従事している。
好きなAWSサービスはAmazon Bedrock、AWS CDK -

カスタマーサクセス本部 CS5課 近藤 諒都
オンプレミスからクラウドまで、サーバー・ミドルウェア・ネットワークを含むシステム基盤の設計・構築・運用・移行を10年経験。
2024年にサーバーワークスへ入社。プリセールス、セキュリティ向上やコスト削減、構築自動化などの技術支援、SREなど多岐にわたる業務を担当。
2025 Japan AWS All Certifications Engineers に選出。
好きなAWSサービスは、AWS CDK と AWS CloudFormation。
選ばれる3つの理由
-
Reason 01
圧倒的な実績数による
提案力とスピード- 導入実績
- 1500 社
- 案件実績
- 28400 件
-
Reason 02
AWS認定の最上位
パートナーとしての技術力
-
Reason 03
いち早くAWS専業に
取り組んだ歴史


