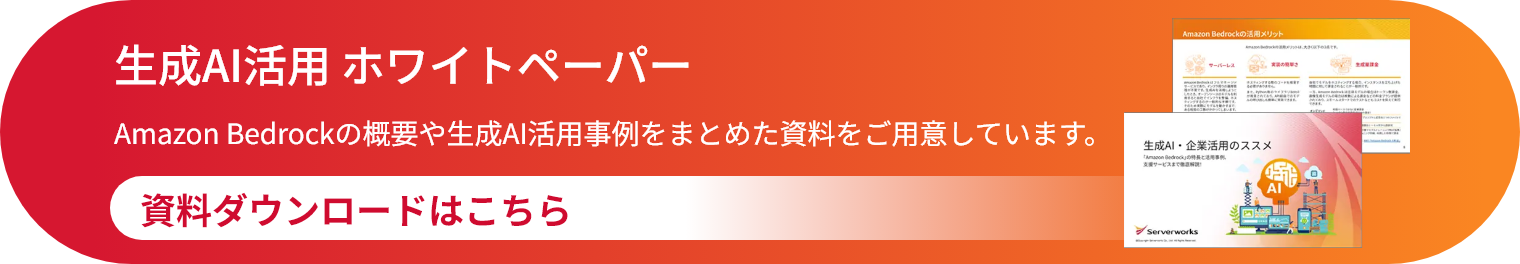AWSの生成AIサービスとは?Amazon BedrockやAmazon SageMakerなどの特徴・選び方・ユースケースを解説

「生成AIをビジネスにどう活かすか?」
いま、多くの企業がこの問いに直面しています。もはや単なる技術検証の段階は終わり、業務プロセスへの本格的な組み込みや、競争優位性を確立するための具体的な活用が求められるようになりました。
しかし、いざ自社の業務に導入するとなると、「どのサービスを選ぶべきか」「セキュリティは大丈夫か」「既存システムと連携できるのか」といった、数多くの課題が立ちはだかります。
本記事では、こうした課題を解決する強力な選択肢として、アマゾン ウェブ サービス(AWS)の生成AIサービスに焦点を当て、AWSが提供する主要サービスの特徴から、目的別の選び方、具体的なユースケースまでを分かりやすく解説します。
この記事でわかること
- Amazon BedrockやAmazon SageMakerなど、AWSの主要な生成AIサービスの違いと特徴
- 「とにかく早く試したい」「自社データで学習させたい」といった目的別の最適なAWS生成AIサービスの選び方
- 顧客対応の自動化や議事録の要約など、すぐに実践できるビジネス活用ユースケース
生成AI活用が加速する今、AWSを選ぶべき理由
生成AIの活用が進む今、どのプラットフォームを選ぶかは、企業の成果を大きく左右する重要なポイントです。AWSの生成AIサービスがどのような強みを持ち、なぜ多くの企業に選ばれているのかを解説します。
生成AI市場の最新動向と企業の関心
生成AIは、いまや一部の先進企業だけの話ではなく、業界や企業規模を問わず、多くの企業が導入を検討する時代になっています。
チャットボットや自動文章生成といったシンプルな使い方を超え、顧客対応の品質向上や業務プロセスの効率化、社内ナレッジの有効活用など、具体的な業務改善につながる事例も増えています。
近年は、PoC(概念実証)にとどまらず、本番環境への導入や業務プロセスへの組み込みまでを見据えた取り組みが、各社の重要な課題となっています。コスト・セキュリティ・運用負荷といった現実的な視点も含め、生成AIをどう活用するかが、ビジネスの成否を左右し始めています。
こうした中、信頼性・拡張性・業務適用のしやすさを兼ね備えたプラットフォームとして、AWSの生成AIサービスが注目を集めています。
AWSの強みと生成AIスタック全体像
AWSの生成AIサービスの導入を検討する際、まず気になるのが、「AWSはそもそも、どんな生成AIサービスを提供しているのか」という点ではないでしょうか。
AWSは、単一のサービスではなく、目的や活用レベルに応じて使い分けできる、複数の生成AIサービスを提供しています。
大きく分けると、「すぐに使える生成AI」と「自社に合わせて作り込める生成AI」の両方をカバーしており、企業ごとの導入段階やニーズに合わせて、柔軟に選択できるのが特徴です。具体的には、以下のようなサービスが用意されています。
- Amazon Bedrock
- ClaudeやMistral AI、Command-R+、AWS独自のAmazon Novaシリーズなど、複数の大規模言語モデル(LLM)をAPI経由で簡単に利用できます。自社データを活用したカスタマイズも可能で、業務に合わせた生成AI活用をスピーディに進められます。
- Amazon SageMaker
- より高度なニーズに応える本格的な開発基盤です。独自の生成AIモデルを学習・微調整・デプロイでき、PoC(概念実証)から本番運用まで、幅広い段階に対応できます。
- Amazon Nova
- AWSが自社で開発した、最新の大規模言語モデル群です。品質やセキュリティ面での信頼性が高く、企業利用にも適しています。
- Amazon Q
- 社内業務や開発支援に特化したAIアシスタントです。ビジネス職向けとエンジニア向けの2つの系統があり、日常業務の中で、生成AIを自然に活用できます。
AWSの強みは、これらのサービスを単体で使うのではなく、必要に応じて組み合わせ、自社の環境や目的に合った最適な構成を実現できる点にあります。
「試してみたい」「自社用に作り込みたい」「業務に組み込みたい」――AWSの生成AIサービスは、そんな多様なニーズに柔軟に応える環境を提供しています。
他クラウドとの比較観点(マルチモデル対応・連携性・セキュリティ)
AWSは、Microsoft AzureやGoogle Cloudと比較しても、次のような強みがあります。
- マルチモデル対応
- 他社製の大規模言語モデル(LLM)はもちろん、AWS独自のAmazon Novaシリーズも選択できます。用途に応じて、最適なモデルを柔軟に組み合わせられる点が特徴です。
- サービス間連携のしやすさ
- 生成AIと、既存のAWSサービス(Amazon S3、AWS Lambda、Amazon Redshiftなど)をスムーズに連携できます。これまでのクラウド基盤を生かしながら、業務に自然に生成AIを組み込める設計です。
- 企業利用に適したセキュリティとガバナンス
- AWS Identity and Access Management(IAM)やAmazon VPC、AWS Key Management Serviceなど、AWS全体のセキュリティ基盤を、そのまま生成AIにも適用できます。機密データの管理やアクセス制御も含め、企業のガバナンス要件にしっかり対応できるのが特徴です。
生成AIを業務に本格的に組み込むには、単に「試す」だけでなく、現実的な構成力と管理体制が欠かせません。その点、AWSは、ビジネス活用を前提とした安心感と拡張性を兼ね備えた、信頼できる選択肢と言えます。
AWSの主な生成AIサービスとその役割
AWSは、企業の生成AI活用を支援するために、目的や利用フェーズに応じて使い分けできる複数のサービスを提供しています。
「すぐに試してみたい」「独自のモデルを育てたい」「業務にしっかり組み込みたい」など、企業ごとに異なる多様なニーズに合わせて、最適な構成を柔軟に選べるのが特徴です。
ここでは、代表的なサービスをわかりやすく整理します。
Amazon Bedrock|複数LLMをAPIで呼び出せる開発基盤
Amazon Bedrockは、Claude、Mistral AI、Command-Rといった有力な他社の大規模言語モデル(LLM)に加え、AWS独自のNovaシリーズも含めた複数のモデルを、API経由で簡単に呼び出せるプラットフォームです。
「どのモデルを選べばいいかわからない」「まずは試してみたい」といった企業でも、Amazon Bedrockを使えば、環境構築やモデルの学習なしで、すぐに生成AIの効果を確認できます。
必要に応じて自社データを活用したカスタマイズも可能で、汎用的な生成AIはもちろん、業務に特化したモデルまで、目的に合わせて柔軟に展開できるのが特徴です。
Amazon SageMaker|生成AIモデルの学習・デプロイ基盤
Amazon SageMakerは、自社に合わせた生成AIモデルを開発・学習・運用するための本格的な基盤です。「自社の業務やデータに完全に合わせたモデルを構築したい」「生成AIの精度や仕様を細かくコントロールしたい」といったニーズに応える、AWSの中でも最も高度な選択肢です。
以下のように、企業の導入段階や開発リソースに応じて活用できるツールも用意されています。
- Amazon SageMaker JumpStart
- 学習済みモデルやテンプレートを活用し、PoC(概念実証)をスピーディに進められるツールです。「まずは短期間で試してみたい」「最小限の手間で生成AIの効果を検証したい」といった場面に適しています。
- Amazon SageMaker Canvas
- ノーコードでAI分析や予測が行えるツールです。開発知識がなくても、ビジネス職が自ら生成AIやデータ分析を業務に活用できるため、現場レベルでのDX推進にも役立ちます。
Amazon SageMakerは、専門性の高い開発用途からノーコードの業務活用まで、企業のレベルや目的に合わせて段階的に活用できる柔軟な環境を提供します。
Amazon Nova|AWS最新の基盤モデル(LLM)ファミリー
Amazon Novaは、AWSが独自に開発した最新の大規模言語モデル(LLM)シリーズです。
ChatGPTの基盤であるOpenAIのモデルや、Llama、Claudeといった有力なLLMと同じカテゴリに位置づけられますが、「AWS基盤上で利用することを前提に設計されたLLM」である点が大きな特徴です。セキュリティやプライバシーの制御がしやすく、企業独自の要件に合わせたカスタマイズや連携も柔軟に行えます。
また、Amazon NovaはAmazon Bedrockから簡単に呼び出せるほか、Amazon SageMakerと組み合わせて、より高度な学習や最適化も可能です。「外部LLMへの依存を減らしたい」「AWS環境で安全に生成AIを活用したい」といった企業にとって、Amazon Novaは有力な選択肢のひとつです。
Amazon Q|生成AIを使った業務支援・開発支援アシスタント
Amazon Qは、社内業務や開発現場に、生成AIを自然に組み込むためのアシスタントサービスです。用途に合わせて、次の2つの系統が用意されています。
- Amazon Q Developer
- 開発者向けの生成AI支援ツールです。コード補完やナレッジ検索、設計支援などを通じて、エンジニアの生産性向上をサポートします。
- Amazon Q Business
- ビジネス職向けのアシスタントです。社内文書の要約やナレッジ検索、問い合わせ対応の効率化など、日常業務の改善に役立ちます。
Amazon Qを使えば、特別なAI開発の知識がなくても、業務の現場に無理なく生成AIを取り入れ、実際の生産性向上につなげることができます。
AWS for Data|生成AI活用を支えるデータ基盤群
生成AIを本格的に活用するためには、モデルだけでなく、学習や運用を支えるデータ基盤が不可欠です。特に、本番環境への導入や自社データを活用したカスタマイズを考えるタイミングでは、AWSのデータ基盤をどう活用するかが重要なポイントになります。
AWSでは、以下のようなデータサービスを組み合わせることで、生成AIの学習や運用を、安全かつ効率的に支えられます。
- Amazon S3
- 柔軟でスケーラブルなデータ保存基盤。学習データや生成結果を効率よく管理できます。
- Amazon Athena
- サーバーレスで手軽にデータ分析を実行。生成AIと連携した分析も容易です。
- Amazon Redshift
- 高性能なデータウェアハウス。大規模データを高速に処理し、生成AIの精度向上に活用できます。
- AWS Glue
- データ連携や加工処理を自動化。複数システム間のデータ整備を効率化します。
これらを活用することで、社内外のデータを効果的に生成AIに取り込み、業務に即した高品質なモデル構築や安定した運用が実現できます。
AWSは、モデル・開発基盤・業務支援だけでなく、こうしたデータ基盤まで含めて一体で提供しているため、段階的かつ安全に生成AIを業務へ組み込める環境が整っています。
目的別|AWS生成AIサービスの選び方
AWSの生成AIサービスは多機能で選択肢も豊富ですが、「何をしたいか」によって最適なサービスは明確に異なります。ここでは、よくある目的別に、どのサービスを選ぶべきかを整理します。
とにかく早く試したい
生成AIの効果や可能性を、スピーディかつ簡単に試したい場合は、Amazon Bedrockが最適です。初期設定やモデル学習は不要で、API経由で複数の大規模言語モデル(LLM)をすぐに呼び出せます。
Claude、Mistral、Command-R、AWS独自のAmazon Novaシリーズなどから用途に合わせて選択でき、「まずは試す」から「業務に組み込む」までスムーズにステップアップできます。
社内データで学習・チューニングしたい
自社の業務やデータに合わせて、精度の高い生成AIを実現したい場合は、Amazon SageMakerが有効です。自社データを使ったモデルの学習や微調整(ファインチューニング)ができ、業界特有の表現や専門用語にも柔軟に対応できます。
Amazon SageMaker JumpStartを使えば、学習済みモデルを活用して、PoC(概念実証)を短期間で進めることも可能です。
ナレッジ活用や社内支援に使いたい
生成AIを開発するだけでなく、日常業務や社内ナレッジ活用にも生かしたい場合は、Amazon Qが適しています。
開発者向けのAmazon Q Developerは、コーディング支援やナレッジ検索を通じて、開発現場の生産性を高めます。ビジネス職向けのAmazon Q Businessは、社内文書の要約や情報検索、問い合わせ対応を効率化できます。
AWS生成AIサービス比較表(導入スピード/自由度/学習可否/コスト/用途)
以下は、主要なAWS生成AIサービスの特徴を簡単に比較したものです。
| 項目 | Amazon Bedrock | Amazon SageMaker | Amazon Q |
|---|---|---|---|
| 導入スピード | ◎ 即利用可能 | △ PoC・設計が必要 | ◎ 即利用可能 |
| カスタマイズ自由度 | ○ 自社データ活用・一部調整可能 | ◎ 独自モデル学習・細かな設計可能 | △ 業務設定レベルのカスタマイズ可能 |
| 学習・チューニングの可否 | 一部対応 | 完全対応 | 対応なし(事前学習済みモデル利用) |
| コスト感(初期導入) | 低コストで始めやすい | 開発・学習コストが必要 | 低コストで始めやすい |
| 主な活用用途 | 試行・業務適用 | 高度な業務特化・独自開発 | 業務効率化・ナレッジ活用 |
AWSは、単に「1つの生成AIサービスを選ぶ」のではなく、目的や段階ごとに最適なサービスを組み合わせて活用するのがポイントです。
AWS生成AIの実践ユースケース集
AWSの生成AIサービスは、単なる技術導入を超え、実際のビジネス現場で具体的な成果を生み出す段階に入っています。以下、国内企業の事例をもとに、特にニーズの高い3つのユースケースを紹介します。
顧客対応(FAQボット・多言語チャット対応)
①生成AIとチャットボットの活用で業務効率を大幅改善
社内に蓄積された膨大な情報リソースを活用し、生成AIを組み込んだチャットボットを短期間で内製開発することで、情報検索や文章の校正、デザイン作成まで、幅広い業務の効率化が可能になります。複数の大規模言語モデル(LLM)を活用することで、営業活動や社内業務における情報活用のスピードと精度が大きく向上します。
②生成AIチャットボットで非エンジニア層にも活用を拡大
Amazon Bedrockを活用したSlack連携のAIチャットボットを社内に展開することで、非エンジニア層にも生成AIの活用が広がり、業務効率や生産性の向上につながります。
社内業務支援(議事録要約・文書検索)
①生成AI基盤の導入で議事録作成を大幅効率化
全社DXの一環として、Amazon Bedrockを活用した生成AI基盤を構築することで、議事録作成の自動化を実現します。従来の手作業と比べて大幅な時間削減が可能になり、社員がより創造的な業務に集中できる環境づくりが可能です。
②幅広い業務を支援する生成AIアプリケーションを短期間で内製開発
議事録作成や規程検索、チャット、文章生成、翻訳、画像生成など、幅広い業務を支援する生成AIアプリケーションを自社内で短期間に開発することで、大規模な組織においても、生成AIを効率的かつ安全に活用できる環境が整備できます。
まとめ|AWSの生成AI活用は「選定力」と「組み合わせ」がカギ
複数のモデルや基盤、業務支援ツールを組み合わせてこそ、自社の目的や課題に合った最適な環境が構築できます。重要なのは、生成AIそのものの性能だけでなく、「自社の業務」「利用するモデル」「実装設計」をどう組み合わせるかです。この設計次第で、競争優位性が大きく左右されます。
生成AIは導入すれば終わりではなく、以下のような段階的なアプローチが欠かせません。
- PoC(概念実証)で効果やリスクを見極める
- 目的や用途に応じて最適なサービスを選定する
- 本番環境への構築と業務への組み込みを設計する
- 運用しながら継続的に改善・最適化する
AWSは、この一連の流れをスムーズに進めるためのサービスと環境を提供しています。 自社の状況に合わせて「選定力」と「組み合わせの設計力」を発揮することが、生成AI活用を現実のビジネス成果につなげるカギです。
詳細はこちら >> 生成AIソリューション
詳細はこちら >> 生成AI PoC支援
詳細はこちら >> AI駆動開発業務トレーニング